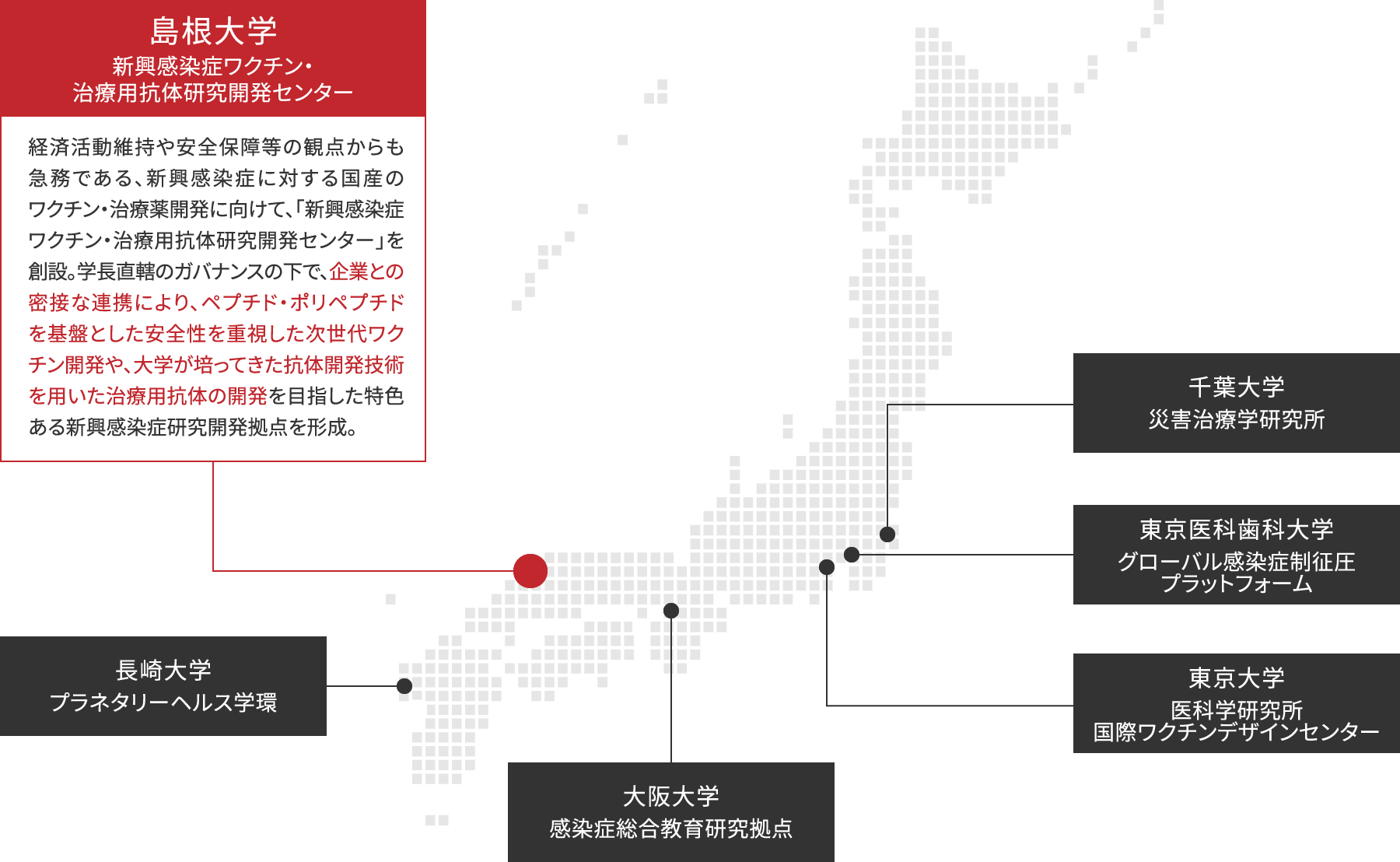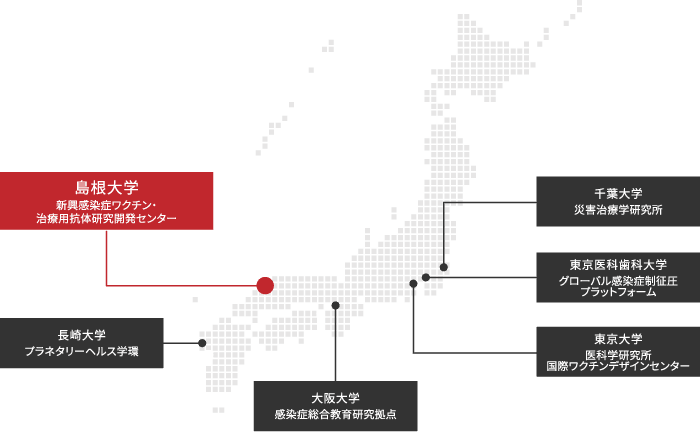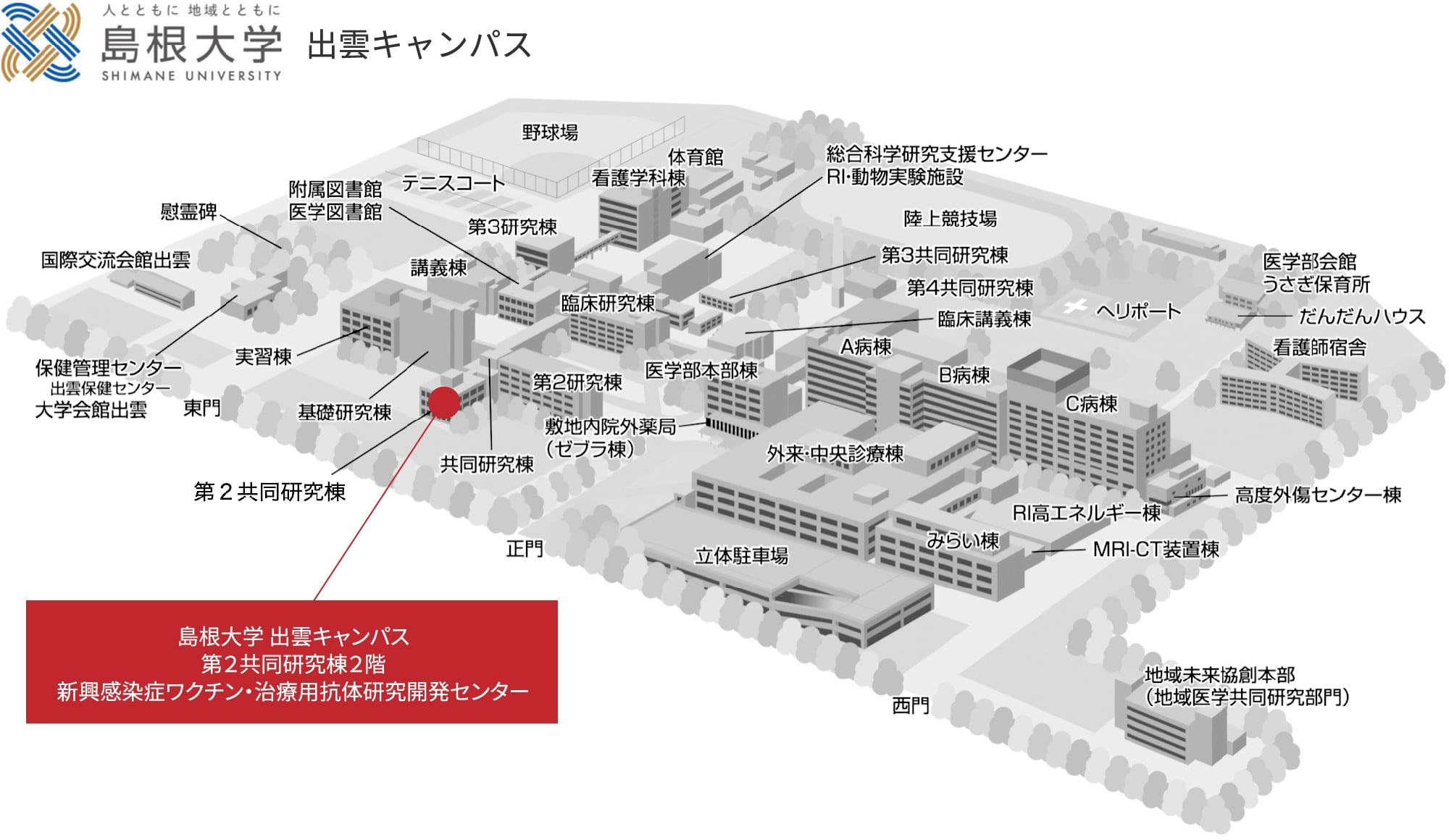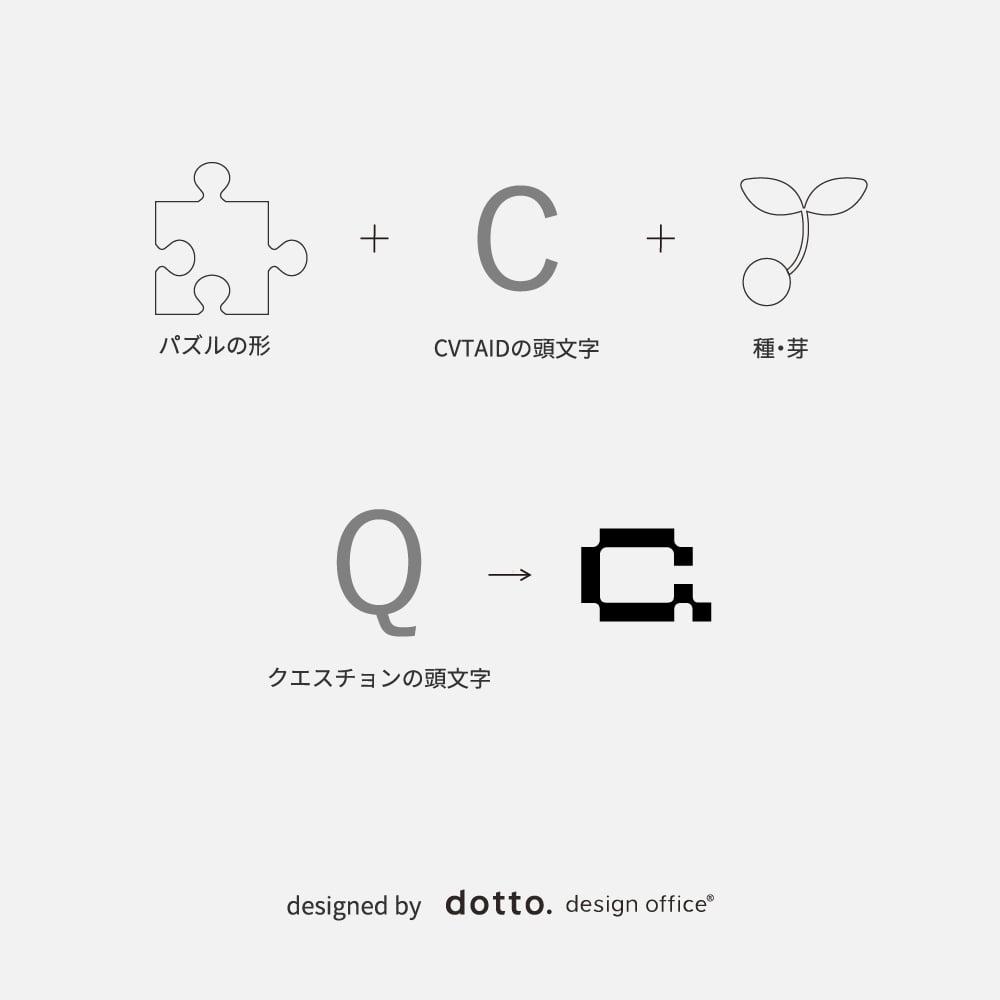島根大学は、高度なタンパク質発現・精製および抗体作製技術を有し、高純度のタンパク質を使用して高品質な抗体を作製してきました。これらの抗体は、世界中の研究機関に広く供給され、研究の発展に貢献しています。これらの高度な技術を基盤として、基礎研究用途にとどまらず、抗体医薬品としての開発・提供を目指し、地方銀行系ファンドから1億5千万円の資金調達を実現し、平成30年3月に島根大学発ベンチャー企業「株式会社 mAbProtein(マブプロテイン)」を設立しました。
■ ワクチン開発
令和2年4月27日、三重大学、京都大学、長崎大学、そして旭化成(株)が協力し、次世代ワクチン開発のための強固なオープン・クローズコンソーシアムを設立しました。このコンソーシアムは、がんワクチンの臨床試験経験を持つ大学と、優れたデリバリー基材を有する企業のそれぞれの強みを結集しています。
このワクチン開発プラットフォームでは、RNAワクチンとは異なる戦略に基づき、安全性を重視し、組換えタンパク質およびペプチドを用いた小児にも接種可能な次世代ワクチン開発を進めています。特色として以下が挙げられます。
- ①国内での開発が完了可能(旭化成(株)のデリバリー基材を使用)
- ②コールドチェーンを必要としない室温流通可能な製剤開発
- ③デリバリー基材の特性により、免疫組織への効率的な移行を実現し、抗体価の上昇、長期間持続(マウスで1年間持続)、中和活性および免疫記憶の誘導に成功
- ④生体物質を骨格としたデリバリー基材により、副反応の可能性が低い
以上、新型コロナウイルス感染症に対するマウス実験を完了し、特許出願しました。
このプラットフォームにより、次世代ワクチンの迅速な開発と社会実装が期待されています。
■ 治療用抗体開発
新型コロナウイルスの細胞感染を阻害する中和活性を持つ抗体を開発しました。この抗体は従来株だけでなく、デルタ株を含む多くの変異株にも対応可能で、現在使用されている中和カクテル抗体と同等の高い親和性(1~4nM)を有しています。これらのいわゆる「スーパー抗体」は、すでに治療用抗体としてヒト化に成功しています。
これまで培ってきた多くの技術をさらに向上させ、次に起こり得る全世界規模の感染症危機に備えるため、研究開発を一層推進していきます。